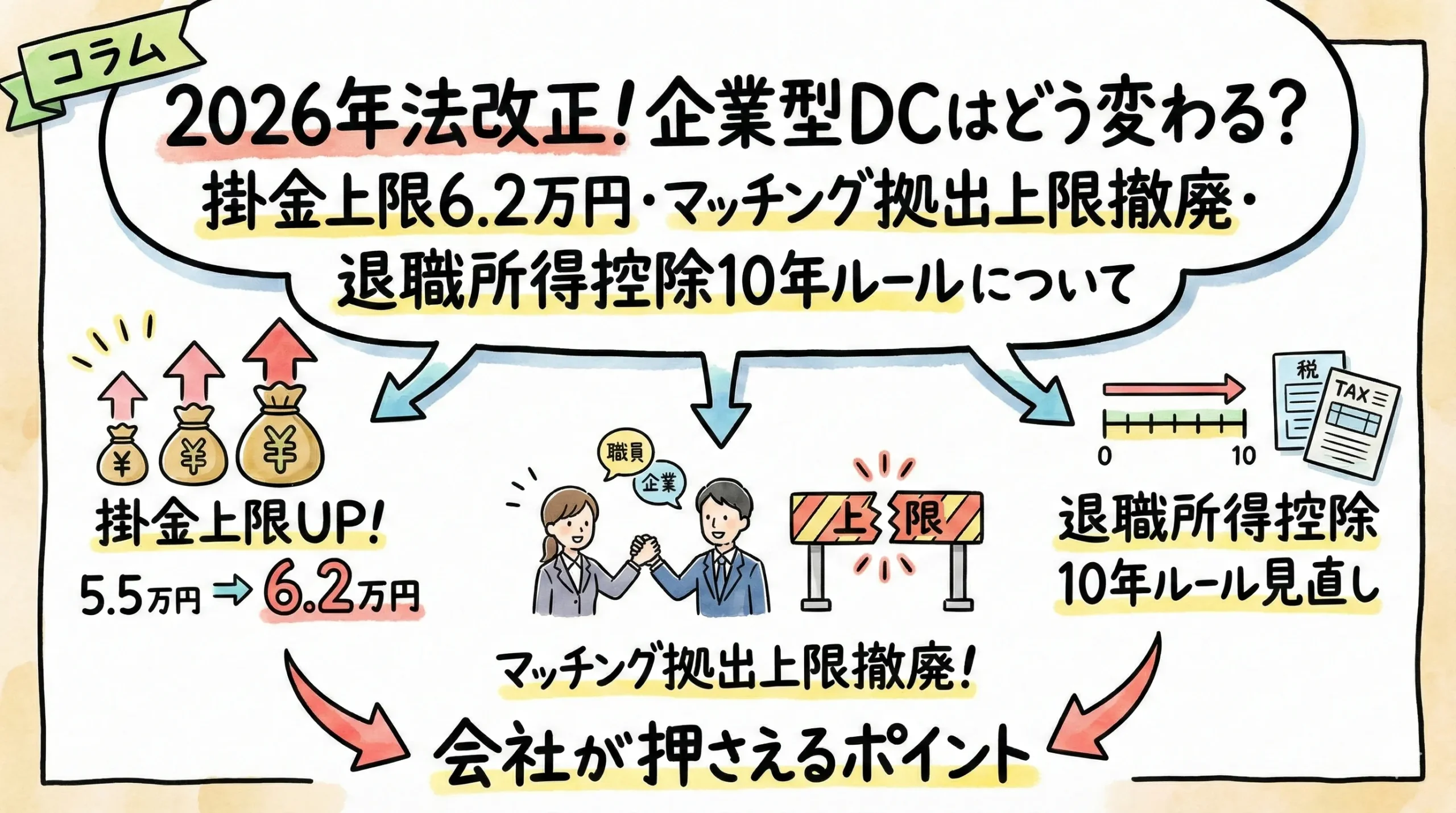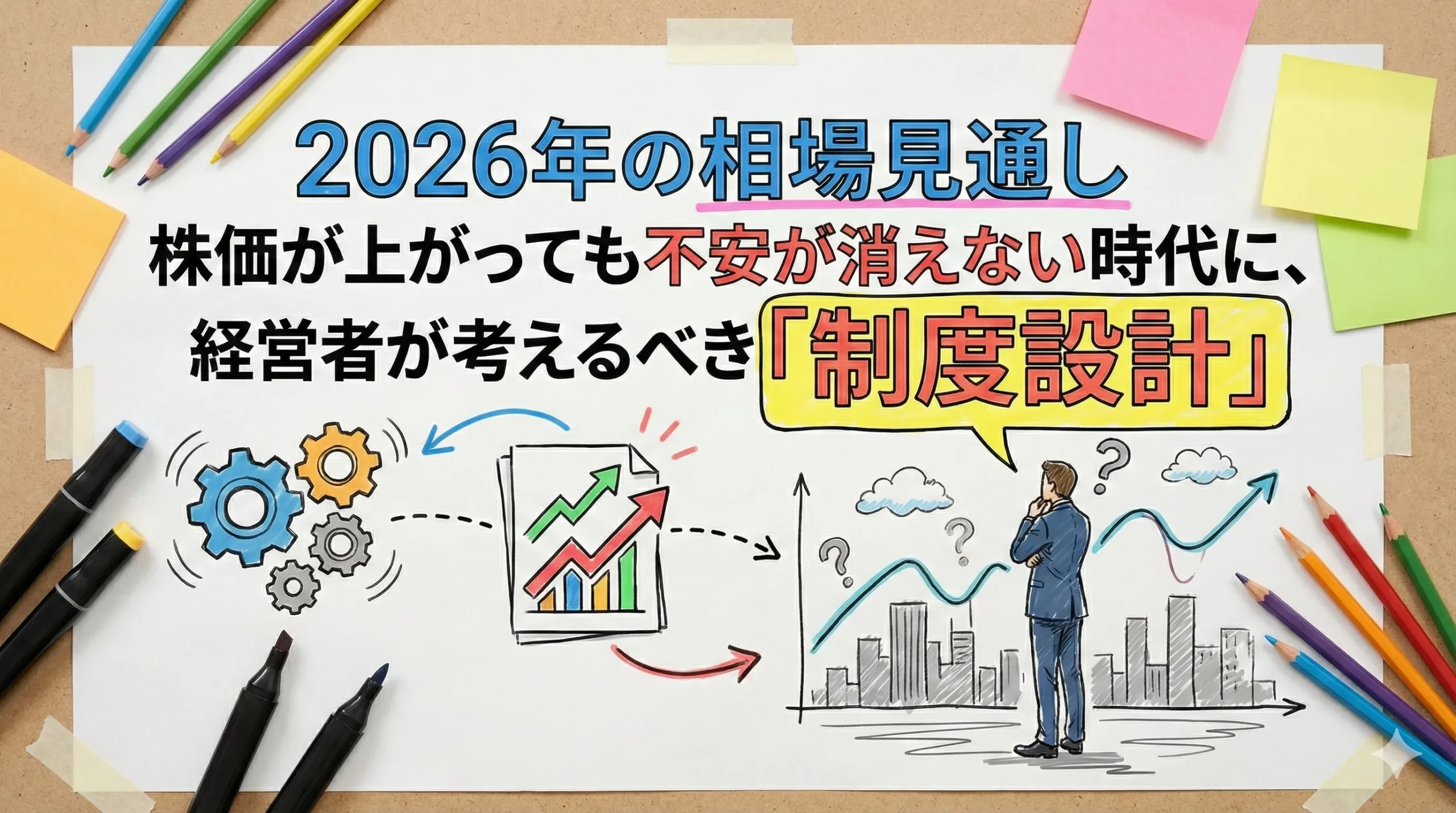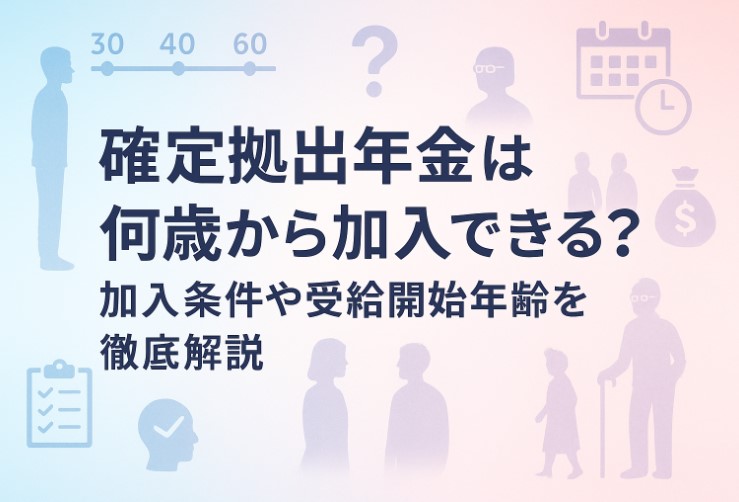「外国人従業員でも企業型確定拠出年金に加入できる?」「帰国する場合はどうすれば良い?」などと悩んでいませんか。
実際、外国人従業員も、条件を満たせば企業型確定拠出年金に加入できます。また、帰国時には、脱退一時金の受け取りやiDeCoへの移換などの選択も可能です。
この記事では、企業型確定拠出年金の基本から、外国人従業員の帰国・退職時の対応、選択制DCの活用方法、導入時の注意点までを詳しく解説します。
外国人従業員を雇用している企業が、制度を安心して導入・運用するためのポイントが分かります。ぜひ参考にしてください。
なお、導入を検討している場合は、実績豊富な専門機関に相談することで、制度設計から運用までをスムーズに進められます。
株式会社マウンティンでは、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入から運用まで、ワンストップでサポートいたします。
これまでに900社以上*の企業様の導入を成功に導いた実績があり、税理士や社会保険労務士、CFPなどの専門家が在籍するグループの強みを活かし、貴社の課題に最適な支援を提供いたします。
*2025年8月時点
【このような方へおすすめ】
・税負担を減らしたい
・社会保険料を減らしたい
・福利厚生を拡充したい
・退職金対策、資産形成をしたい など
まずは、お気軽に資料請求・お問い合わせください!
外国人従業員も加入できる!企業型確定拠出年金の基本
厚生労働省が公表した令和6年10月末時点の外国人雇用状況によると、国内で働く外国人労働者は約230万人と過去最多を記録しました。*グローバル化が進む現在、企業は外国人従業員にも日本人と同様に、公平な待遇を提供することが求められています。
近年では、企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入する企業が増えており、外国人従業員も一定の条件を満たせば加入が可能です。企業型確定拠出年金は、資産形成の機会を提供する制度として注目されています。
ここでは、企業型確定拠出年金の基本的な制度内容について紹介します。
*出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)|厚生労働省
企業型確定拠出年金は私的年金の一つ
企業型確定拠出年金は、企業が従業員の老後資産形成を支援する私的年金制度です。企業が毎月の掛金(拠出額)を負担し、その資金を従業員が自ら運用します。
掛金の額は決まっている一方、将来の受取額は決まっておらず、運用成果によって変動するという特徴があります。そのため、投資信託など値動きのある商品を選べば資産が大きく増える可能性もありますが、損失を被るリスクもともないます。
また、企業型確定拠出年金は老後資金の形成を目的とした制度であり、原則として60歳以降にしか給付を受け取れません。途中で退職した場合でも、年金としての給付を早めることはできないので注意が必要です。
加入対象は厚生年金の被保険者
企業型確定拠出年金への加入は、厚生年金の被保険者であることが条件です。正社員だけでなく、一定の条件を満たした契約社員やパートタイマー、そして国籍を問わず適用されるため外国人労働者も対象に含まれます。
つまり企業が制度を導入している場合、その企業に在籍し、かつ厚生年金に加入していれば原則として加入が可能です。
例えば、フルタイム勤務の外国人従業員が社会保険に加入していれば、日本人従業員と同じく企業型確定拠出年金の対象となります。一方、短時間勤務で社会保険に加入していない場合は、加入要件を満たさない可能性があるため確認が必要です。
ポータビリティ制度で転職や退職にも対応
企業型確定拠出年金には、転職や退職の際にも資産を持ち運べるポータビリティ制度があります。企業を離れたあとでも年金資産を失うことなく、将来に向けた資産形成を継続することが可能です。
近年では、外国人従業員の採用が進む一方で、契約満了や帰国などにより比較的短期間で退職に至るケースが一定数存在します。こうした背景を踏まえると、ポータビリティ制度の活用は、外国人従業員にとっても有用だといえます。
もし、転職先が企業型確定拠出年金を採用していれば資産の移換が可能であり、そうでない場合でも、iDeCoへ資産を移して運用を継続できます。こうすることにより、外国人従業員でも安心して日本の年金制度を利用し、将来の生活設計を立てられます。
帰国する外国人従業員の企業型確定拠出年金はどうすれば良い?
では、企業型確定拠出年金に加入していた外国人従業員が帰国する際、積み立てた年金資産はどうなるのでしょうか。
帰国にともなう対応としては、脱退一時金を受け取る、個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業年金連合会に移換するなどの選択肢があります。それぞれに条件や手続きがあるため、事前に必要な情報を把握しておくことが必要です。
以下では、それぞれの対応方法について詳しく解説します。
脱退一時金を受け取る
帰国する外国人従業員が企業型確定拠出年金の資産を清算する方法として、脱退一時金の受け取りがあります。
脱退一時金は、積み立てた年金資産を一時金として受け取る仕組みであり、日本に住み続けない場合でも資産を活用できます。老後を日本で迎えることを前提としない外国人従業員の場合、将来まで資産を留め置くよりも、帰国時に現金化する選択が現実的といえます。
しかし、脱退一時金は帰国後に日本の年金制度に引き続き加入できない事情などを考慮し、例外的に認められている措置です。受け取りには、特定の条件を満たす必要があります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換する
脱退一時金の要件を満たさない外国人従業員が帰国する場合、企業型確定拠出年金の資産を継続して管理するには、個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業年金連合会への移換が必要になります。
iDeCoに移換したあとは、新たに掛金を拠出できず、運用のみの管理となる点に注意が必要です。また、加入資格を喪失して6ヶ月以内に移換しない場合は自動移換の対象となるため、計画的な対応が求められます。
もう一つの選択肢として、企業年金連合会が運営する通算企業年金制度に資産を移すことも可能です。通算企業年金は、退職などで企業型確定拠出年金の加入資格を失った人が、蓄積された資産を移し、終身年金として受け取れる制度です。
iDeCoと異なるのは、通算企業年金では本人による運用の選択はできず、企業年金連合会が予定利率に基づいて資産を運用する点です。なお、通算企業年金への移換手続きも、iDeCo同様6ヶ月後の期限があります。
それぞれ手続きに手間やコストがかかるため、可能ならば脱退一時金を選択するのが良いでしょう。
放置すると国民年金基金連合会に自動移換される
転職や帰国後に必要な手続きを行わず放置していると、企業型確定拠出年金の資産は現金化されたうえで国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換された資産は拠出や運用指図ができず、現金のまま管理されます。その一方で、特定運営管理機関による管理手数料は引き続き差し引かれるため、資産が目減りするリスクがあります。
また、60歳以降に老齢給付金を受け取るには一度iDeCoに移換する必要があるため、手続きを怠ったままだと資産の引き出しもスムーズに進みません。
そのため、外国人従業員が帰国する際は事前に手続きを行い、資産を適切に管理することが重要です。
脱退一時金制度の仕組み
企業型確定拠出年金の資産は本来、60歳以降に老後資金として受け取ります。しかし、外国人従業員が帰国して日本の年金制度に加入し続けられない場合、積み立てた資産を老後まで保有し続けるのは現実的ではありません。
そうした状況に対応するため、脱退一時金という制度が設けられています。特定の条件を満たす場合に、企業型確定拠出年金の年金資産を脱退一時金として受け取ることが可能です。
以下では、実際に脱退一時金を受給するための条件や方法、注意点について詳しく紹介します。
脱退一時金の受給条件
脱退一時金を受け取るには、企業型確定拠出年金やiDeCoの加入状況、資産額、年齢、国籍など複数の条件を満たす必要があります。制度上は2つのケースに分けて要件が定められており、どちらも該当条件をすべて満たしていなければ申請はできません。
なお、2022年5月法改正により、下記のとおり要件緩和となりました。
【個人別管理資産額が1.5万円以下のケース】
- ・企業型DCやiDeCoの加入者・運用指図者でないこと
- ・企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
【資産額が1.5万円を超えるケース】
- ・60歳未満であること
- ・国民年金の任意加入資格が無いこと
- ・障害給付金の受給権者ではないこと
- ・通算拠出期間が5年以下またはDC年金資産が25万円以下であること
- ・企業型DCに入っていた人は、資格喪失日の翌月から起算して6ヶ月を経過していないこと
- ・企業型DCの加入者・運用指図者ではないこと
※注意事項※
1)日本にある銀行口座にのみ円通貨で支給されるので、帰国後半年ほどは日本の口座を残しておく必要があります。
2)企業型資格喪失後に、加入者本人がコールセンターに脱退一時金支給申請書類を請求し、自身で裁定申請を行う必要があります。
上記のように受給条件は複雑であるため、対象者は退職や帰国のタイミングでしっかりと確認することが重要です。
脱退一時金の受け取り方法
脱退一時金を受け取るには、加入者本人が自らコールセンターに書類を請求し、申請手続きを進める必要があります。そのため、制度上の要件に該当する場合は、退職後すみやかに手続きを始めることが重要です。
手続きは、企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関、あるいは国民年金基金連合会に対して行います。それぞれの機関によって必要書類や申請先が異なるため、事前に確認が必要です。また、申請にあたっては事務手数料がかかる場合もあります。
脱退一時金を受け取る際は、申請先と手続き内容を確認し、期限内に漏れなく対応するようにしましょう。
脱退一時金受給時の注意点
脱退一時金の請求時には、注意すべき点がいくつかあります。
脱退一時金を60歳前に受け取ると、その給付金は一時所得として課税対象になります。退職所得控除などの優遇措置は適用されず、課税額が大きくなるおそれがあります。
また、退職後に備える資産が目減りすることで、老後生活への備えが不足するリスクも否定できません。
さらに、脱退一時金は日本国内の銀行口座への円建てでの支給となります。帰国を予定している外国人従業員は、帰国後も半年ほどは日本の銀行口座を残すようにしてください。
なお、勤続年数が3年未満で企業型確定拠出年金の資格を喪失した場合、企業型年金規約によっては拠出された掛金が事業主に返還される場合もあります。対象者は旧勤務先に確認し、制度の規約内容を確認するようにしてください。
外国人従業員がいる企業が企業型確定拠出年金を導入する際のポイント
外国人従業員を雇用する企業が企業型確定拠出年金を導入する際には、制度設計や情報提供の面で特に配慮が必要です。
年金制度は専門用語や特有のルールが多く、日本語を母語としない従業員にとっては理解のハードルが高くなることもあります。
ここでは、外国人従業員を雇用している企業が、企業型確定拠出年金の導入を検討する際に留意すべき点について解説します。
情報は丁寧に分かりやすく伝える
企業型確定拠出年金を導入する際は、外国人従業員に対して制度内容を丁寧に分かりやすく伝えるようにしてください。正確に伝わっていなければ制度を十分に活用できず、不信感や混乱を招く原因にもなりかねません。
具体例としては、専門用語を分かりやすく説明したり、母国語で書かれた案内資料を用意したりすることで、制度への理解の促進が期待できます。加えて、必要に応じて通訳を交えた説明会を実施、またはFAQ形式でポイントをまとめた資料を配布するなどの工夫もおすすめです。
ただ制度を導入して終わるのではなく、従業員が正しく理解し、自信をもって活用できるようにすることが企業の責任といえます。
制度が自社に合うかをよく検討する
企業型確定拠出年金を導入する際には、制度の内容が自社に適しているかを慎重に検討することが必要があります。制度そのものが優れていても、企業の体制や人員構成と噛み合わなければ、利用が進まずコストだけが先行する恐れがあります。
例えば、契約期間が短い企業や、帰国を前提とした人材が多い場合には、長期の資産形成を前提とする企業型確定拠出年金が目的とずれてしまう場合があります。
なお、制度設計においては、一定の職種や勤続年数を加入条件として設定することが認められています。
実際に、外国人従業員が将来的に帰国する可能性を考え、外国人従業員を加入対象者から外す企業が多いようです。その際は、制度上の不利益を補うための措置を講じるのが一般的です。
例えば、外国人従業員には企業型確定拠出年金を適用せず、代わりに掛金相当額を「ライフプラン手当」として給与に上乗せするケースがあります。
その一例として、外国人従業員には企業型確定拠出年金を適用せず、代わりに掛金相当額を「ライフプラン手当」として給与に上乗せしているケースもあります。
外国人従業員がいる企業も利用できる!選択制企業型DCの魅力
外国人従業員を含む多様な人材を受け入れる企業では、従業員それぞれのライフスタイルや価値観に応じた制度設計が求められます。
そのような状況で注目されているのが、「選択制」の企業型確定拠出年金を導入する方法です。選択制企業型DCは、従業員が給与の一部を年金原資として拠出するかどうかを選択できる制度です。
ここでは、選択制企業型DCの主なメリットを3つ紹介します。
多様な働き方に応じて拠出を選択できる
選択制企業型DCの最大の特長は、収入状況や将来設計、家族構成などのそれぞれの事情に応じて、従業員が自ら拠出の有無や金額を選べる点にあります。特に外国人従業員のように、在留期間が限られていたり、本国との二重生活があったりする場合には、この柔軟な制度が大きなメリットとなります。
例えば、子育てや仕送りなどで毎月の可処分所得に余裕がない場合、従業員は拠出を見送ることが可能です。一方、老後の備えを重視する場合は、積極的に拠出を選択できます。
このように選択制企業型DCは、従業員の多様な働き方と将来設計に対応できる柔軟な年金制度として、高い実用性を持っています。
| 一般的な企業型DC(通常型) | 選択制企業型DC | |
| 概要 | 企業が掛金を拠出する一般的な確定拠出年金制度 | 最近採用されることが増えている柔軟なタイプ |
| 加入方法 | 対象者全員が自動的に加入 | 従業員が加入するかどうかを自分で選べる |
| 掛金の負担 | 企業が全額を負担 | 給与の一部を掛金として拠出 |
企業の福利厚生を手厚くできる
選択制企業型DCを導入することで、企業は従業員に対してより柔軟で実質的な福利厚生制度を提供できます。単に制度を整えるだけでなく、従業員のニーズや価値観に応じた選択肢を設けることが、企業の魅力向上や人材確保にもつながります。
選択制企業型DCでは、掛金を拠出するかどうかを本人が判断できるため、従業員が「自分に合った制度を選べている」と実感しやすくなります。結果として、福利厚生が実態に即した価値ある支援として受け止められ、定着率や満足度の向上にもつなげることが可能です。
選択制企業型DCは、実質的な福利厚生の充実を目指す企業にとって特におすすめの選択肢だといえます。
社会保険料の負担を軽減できる
選択制企業型DCでは、従業員が給与の一部を掛金として拠出することで社会保険料の対象となる報酬額が下がり、結果として自己負担の社会保険料を軽減できます。
月額給与の一部を拠出し企業型DCに積み立てた場合、その拠出額は標準報酬月額の対象外となるため、健康保険や厚生年金の保険料の算定基礎から除外されます。その結果、社会保険料の自己負担額が減り、老後資産を準備しながらも目先の所得を確保しやすくなります。
同様に、企業側の保険料負担も軽減されるため、双方にとって費用対効果の高い福利厚生策となります。ただし、報酬額が下がると将来の年金受給額や健康保険給付額に影響することもあるため、制度の導入にあたっては丁寧な説明が欠かせません。
社会保険料の負担軽減という側面からも総合的に考えて、選択制企業型DCは経済的合理性のある制度といえます。

外国人も加入対象となる企業型確定拠出年金で従業員の資産形成を支援しよう
外国人従業員も厚生年金の被保険者である限り、企業型確定拠出年金に加入できます。帰国時には脱退一時金の受給、iDeCoへの移換などの選択肢があり、それぞれ異なるメリットとデメリットがあることから、事前に十分な説明が必要です。
企業が導入する際は、外国人従業員の多様なニーズを考慮し、丁寧で分かりやすい情報提供を心がけてください。特に選択制企業型DCは、従業員が自分の状況に応じて拠出を選択でき、社会保険料の軽減も期待できるため、外国人従業員を雇用する企業におすすめです。
なお、外国人従業員を雇用する企業が企業型確定拠出年金を導入する際は、帰国時の対応など検討すべき点が多岐にわたるため、専門的なサポートを受けることを推奨します。制度設計や運用から従業員への説明まで包括的な支援を受けられ、安心して制度を導入することが可能です。
株式会社マウンティンでは、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入から運用まで、ワンストップでサポートいたします。
これまでに900社以上*の企業様の導入を成功に導いた実績があり、税理士や社会保険労務士、CFPなどの専門家が在籍するグループの強みを活かし、貴社の課題に最適な支援を提供いたします。
*2025年8月時点
【このような方へおすすめ】
・税負担を減らしたい
・社会保険料を減らしたい
・福利厚生を拡充したい
・退職金対策、資産形成をしたい など
まずは、お気軽に資料請求・お問い合わせください!