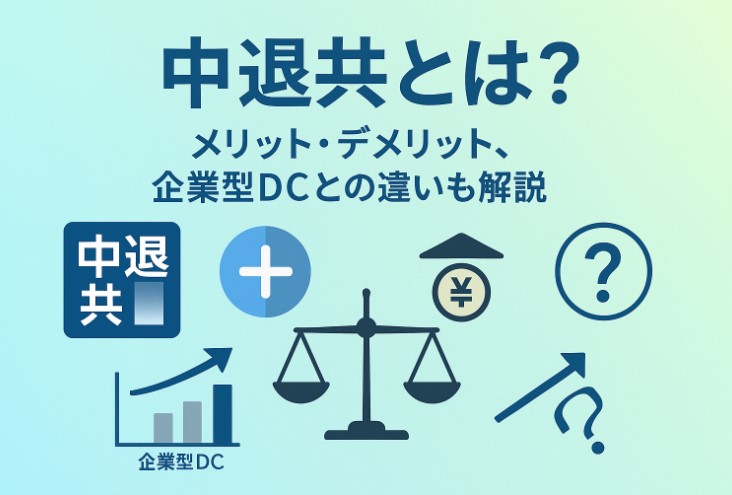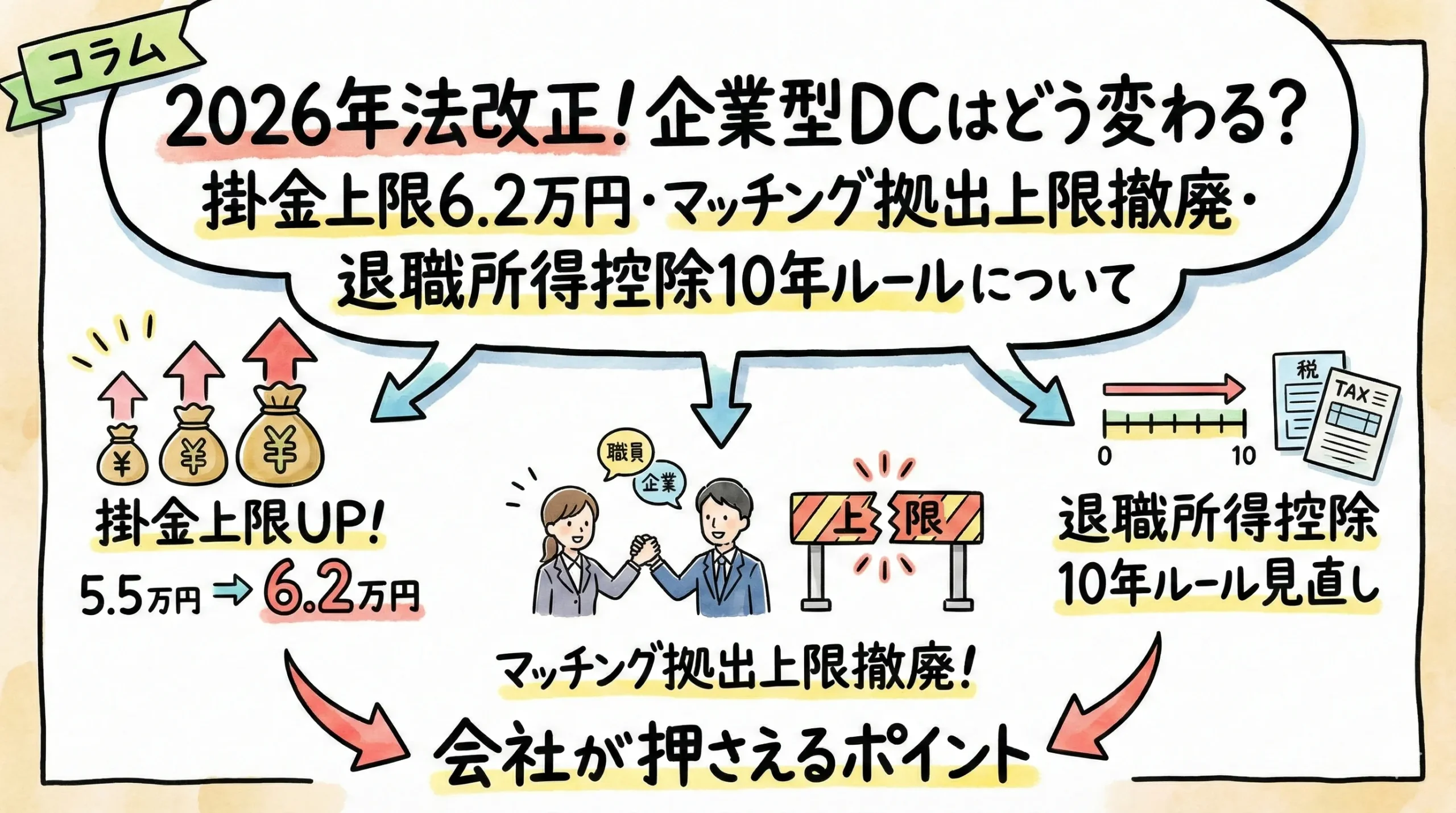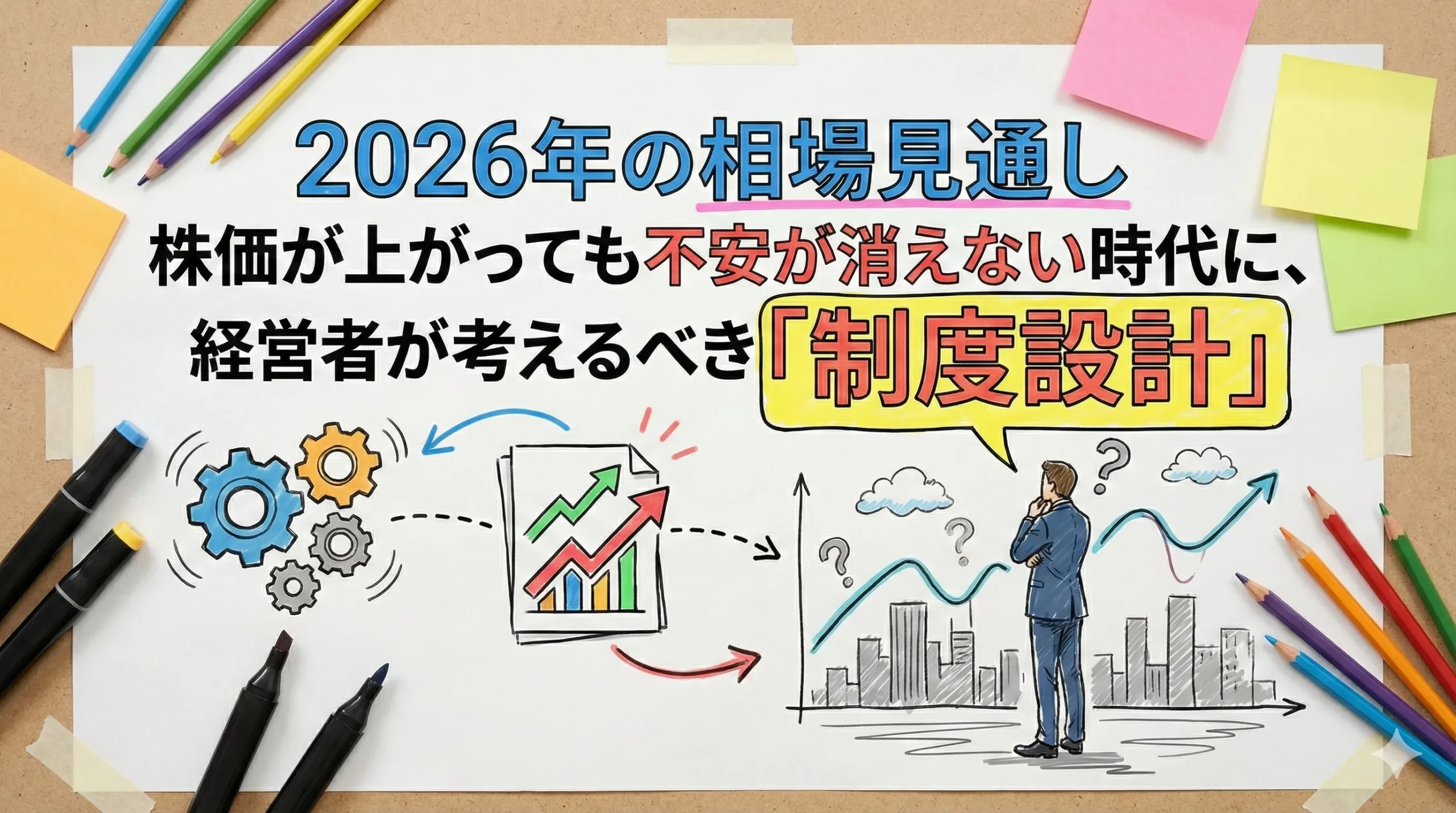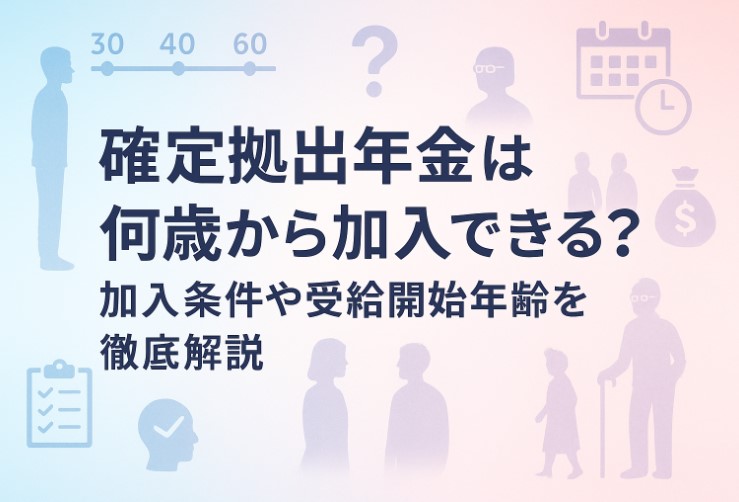中退共とは、独自の退職金制度を従業員に提供するのが難しい中小企業向けの支援制度です。中小企業の事業主が中退共と退職金共済契約を結んで掛金を積み立て、従業員の退職金の準備ができるようになります。
退職金制度を整備したい中小企業にとって有力な制度ですが、メリットもデメリットもあります。
本記事では、中退共の制度概要やメリット・デメリットを、企業側と従業員側に分けて解説します。従業員満足度の向上にさらにおすすめできる「企業型DC」の制度もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
株式会社マウンティンでは、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入から運用まで、ワンストップでサポートいたします。
これまでに900社以上*の企業様の導入を成功に導いた実績があり、税理士や社会保険労務士、CFPなどの専門家が在籍するグループの強みを活かし、貴社の課題に最適な支援を提供いたします。
*2025年8月時点
【このような方へおすすめ】
・税負担を減らしたい
・社会保険料を減らしたい
・福利厚生を拡充したい
・退職金対策、資産形成をしたい など
まずは、お気軽に資料請求・お問い合わせください!
中退共(中小企業退職金共済)とは?
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業のために設けられた退職金制度です。「独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共)」が運営を行っています。
会社が毎月掛金を支払って従業員の退職金を積み立て、従業員が退職となった場合には退職金は中退共から直接支払われる仕組みです。
加入には一定の条件があり、以下の条件を満たす企業のみ加入できます。
| 業種 | 基準 |
| 一般業種 | 常用従業員数が300人以下または、資本金・出資金が3億円以下 |
| 卸売業 | 常用従業員数が100人以下または、資本金・出資金が1億円以下 |
| サービス業 | 常用従業員数が100人以下または、資本金・出資金が5千万円以下 |
| 小売業 | 常用従業員数が50人以下または、資本金・出資金が5千万円以下 |
中退共と特退共の違い
中退共と似た名称の制度の「特退共(とくたいきょう)」がありますが、それぞれまったく別の制度です。
特退共(特定業種退職金共済)は国が提供する退職金制度のひとつで、先行きが読みづらい業界で働く従業員向けに作られました。
特退共は、主に以下の3つの制度があります。
- ・建設業退職金共済制度(建退共)
- ・清酒製造業退職金共済制度(清退共)
- ・林業退職金共済制度(林退共)
それぞれの制度名にあるように、建設業・清酒製造業・林業など特定業種を営む事業主のみが加入できます。条件を満たす中小企業の従業員全員が加入できる中退共とは加入対象者が大きく異なる制度です。
中退共の退職金はいくら?計算式と早見表
掛金納付月数によって計算式が異なる場合がありますが、今回は「20年(240月)加入した会社員が退職したケース」を例に計算します。掛金納付月数が43月以上の場合、中退共の退職金は掛金月額と納付月数から算出した「基本退職金」に「付加退職金」を加えた金額です。
毎月の掛金が10,000円で掛金納付月数が240月の場合、基本退職金は266,660円の10本分で「2,666,600円」です。
一方、付加退職金は、令和7年度の支給率は「0」のため、今回は計算しません。
以下に1年(12ヶ月)ごとの基本退職金を30年まで早見表としてまとめたので、退職金を計算する際の参考になさってください。
1,000円あたり 単位/円
| 月数 | 金額 | 月数 | 円 | 月数 | 円 | 月数 | 円 |
| 12 | 12,000 | 132 | 139,910 | 252 | 281,460 | 372 | 437,640 |
| 24 | 24,000 | 144 | 153,450 | 264 | 296,400 | 384 | 454,130 |
| 36 | 36,000 | 156 | 167,180 | 276 | 311,480 | 396 | 470,700 |
| 48 | 48,170 | 168 | 181,060 | 288 | 326,700 | 408 | 487,600 |
| 60 | 60,820 | 180 | 195,000 | 300 | 342,080 | 420 | 504,580 |
| 72 | 73,710 | 192 | 208,980 | 312 | 357,610 | 432 | 521,710 |
| 84 | 86,760 | 204 | 223,170 | 324 | 373,290 | 444 | 539,020 |
| 96 | 99,950 | 216 | 237,510 | 336 | 389,400 | 456 | 556,470 |
| 108 | 113,230 | 228 | 252,000 | 348 | 405,150 | 468 | 574,060 |
| 120 | 126,560 | 240 | 266,660 | 360 | 421,310 | 480 | 591,790 |
中退共の退職金の手続き方法
中退共に加入していた会社員が退職した場合、企業は以下の流れで手続きが必要です。
- ・被共済者退職届の記入
- ・被共済者退職届の送付
- ・退職金共済手帳の交付
中退共から従業員ごとに送付される「退職金共済手帳」の2枚目にある「被共済者退職届」に以下を記入します。
- ・退職年月日
- ・退職事由
- ・従業員の住所
- ・電話番号
- ・マイナンバー
- ・事業主の住所
- ・電話番号
- ・氏名または名称
次に、従業員の退職日が決まり次第、書留郵便または特定記録郵便などで被共済者退職届を中退共本部保全課に送付します。
退職金共済手帳の3枚目「退職金(解約手当金)請求書」の右上「事業主(共済契約者)記入欄」を記入したうえで従業員に共済手帳を交付すれば、企業側の手続きは完了です。
【企業側】中退共のメリット
中退共には、制度を用意する企業側と制度の恩恵を受ける従業員側、それぞれにメリットがあります。
まず、企業側にとっての中退共のメリットは以下のとおりです。
- ・国による助成が受けられる
- ・掛金を損金に算入できる
国による助成を受けて効率的に福利厚生の準備をしつつ、節税まで可能な点がメリットです。ここからは企業側のメリットの詳細を紹介します。
国による助成が受けられる
中退共制度には、国からの助成金制度が設けられています。新規加入時や掛金を増額するとき、事業主の負担を軽減できる点がメリットです。
- 新規加入掛金助成
- 月額変更(増額)助成
まず、中退共への新規加入時に加入後4ヶ月目から、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間助成してもらえます。
また、18,000円以下の掛金月額を増額変更する企業は増額する金額の3分の1を国から助成してもらうことが可能です。
掛金を損金に算入できる
中退共に加入して企業が払い込んだ掛金は、全額を損金算入できるメリットがあります。
掛金分が損金になれば企業の益金が減少して企業の税負担を抑えられます。また、掛金は給与所得にならないため、従業員の税負担増もありません。
【企業側】中退共のデメリット
ここからは、企業側の視点で、中退共に関するデメリットとメリットを解説します。中退共の導入による企業側のデメリットは以下のとおりです。
- ・社長や役員の人は加入できない
- ・掛金の減額が簡単にはできない
- ・掛金が少なく福利厚生になりにくい
- ・従業員は全員の参加が必要
中退共が企業にとってどのようなデメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
社長や役員の人は加入できない
中退共は中小企業に勤める従業員のための制度であり、後述する企業型DCと違って社長や役員などは加入できません。
社長や役員が将来の年金準備などをしたい場合、企業型DCなど他の制度への加入を別途検討する必要があります。
なお、役員でありながら従業員として賃金を受け取っている「使用人兼務役員」は、例外的に中退共に加入できる可能性があります。
掛金の減額が簡単にはできない
中退共は加入後に掛金の増額・減額が可能ですが、減額は一定の制限が設けられています。中退共の掛金の減額を行いたい場合、従業員の同意が必要です。
仮に従業員の同意が得られない場合は厚生労働大臣の認定書を取得する必要があります。認定書は、現在の掛金月額の継続が著しく困難である認定手続きを経て獲得できます。
あとからの減額が大変であるため、中退共の掛金は慎重に検討しなければいけません。
掛金が少なく福利厚生になりにくい
中退共は従業員の退職金の確保に利用できる制度ですが、掛金は最大で1ヶ月3万円と定められています。1年続けても積み立てられるのは年間36万円、30年間積み立てても累計で1,080万円にしかなりません。
若手の社員にとっては良いかもしれませんが、中堅やベテランなど掛金を積み立てる年数が少ない方は将来の受取額に不十分さを感じる可能性があります。
従業員は全員の参加が必要
中退共は全員加入が原則です。つまり「勤続10年以上だけの者を加入させる」のような特別扱いはできません。
従業員全員分の退職金用の掛金を準備できるか、事前に把握しておく必要があるでしょう。
【従業員側】中退共のメリット
続いて、従業員側のメリット・デメリットを解説します。従業員は、中退共に加入すると以下のメリットを享受できます。
- ・運用すれば利息が得られる
- ・転職した場合に退職金の通算が可能
中退共の導入が従業員の満足度向上が目的の場合、どのようなメリットがあるのか経営側が理解しておきましょう。
運用すれば利息が得られる
中退共はただ掛金を積み立てておけるだけでなく、掛金を積み立てた期間が長いほど将来的に受け取れる金額が大きくなります。
中退共で受け取れる金額には以下の2つがあるためです。
| 基本退職金 | 「掛金月額」「納付月数」に応じて固定的に決められる退職金。予定運用利回り1.0%。 |
| 付加退職金 | 掛金の納付月数43月目と、その後12ヶ月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定める支給率を乗じた額を累計した総額。 |
基本退職金の金利が1.0%あるため、運用期間が長いほど受け取れる退職金が大きくなります。
転職した場合に退職金の通算が可能
中退共に加入している企業間で従業員が転職した場合、退職金の通算が可能です。通常は退職すると退職金が支払われますが、中退共なら次の会社に引き継ぐことでより多くの退職金を受け取れる可能性があります。
ただし、掛金の通算には下記の条件があります。
- ・転職前後の両方の企業が中退共に加入している
- ・掛金が12ヶ月以上納付されている
- ・前勤務先の退職後3年以内に新しい勤務先で中退共に加入する
- ・転職前の企業で退職金を受け取っていない
【従業員側】中退共のデメリット
従業員から見た中退共のデメリットとして考えられるのは、以下の3つです。
- ・短期で退職すると退職金がまったく支給されない
- ・運用利回りが低い
運用利回りが低いため、まとまった退職金を受け取るには長期間の加入が必要である点に注意が必要です。中退共に加入する目的は従業員の待遇向上も含まれるため、従業員側からみた制度の理解も重要となります。
短期で退職すると退職金がまったく支給されない
中退共は、短期で退職してしまうと退職金をまったく受け取れないため注意が必要です。
加入後、掛金の支払いを開始して12ヶ月未満で退職してしまうと、退職金は全額支給されません。
掛金分は掛け捨てになってしまうため、少なくとも12ヶ月以上は働き続ける必要があります。
運用利回りが低い
後述する企業型DCなどほかの制度と比較して、運用利回りが低い傾向にあるデメリットがあります。
中退共の基本退職金の予定利回りは約1%。付加退職金はそのときの金融情勢にもよっては「0」となる年も多く、利回りが高いとはいえません。
加入していた期間が数年程度の場合、ほとんど増えずに掛金とわずかの利息のみの受給に留まる可能性もあります。
従業員満足度を高めるには、企業型DCの導入も検討しよう
従業員満足度を向上させる方法として有力な「中退共」ですが、企業にとっても従業員にとってもデメリットがあります。
企業側にとっては社長や役員の人は加入できない点、従業員にとっては利回りが低く掛金が少ない点が主にデメリットとして挙がります。
福利厚生の充実を通じて従業員満足度の向上を図るなら、中退共だけでなく企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)の導入の検討をおすすめします。
企業型DCとは、企業が掛金を拠出し、従業員自らが運用する私的年金制度です。将来の受取金額は運用成果に応じて異なり、原則60歳になってから受け取れます。元本確保型の定期預金・保険とリスク性の投資信託の選択肢があるため、初心者でも運用しやすいメリットがあります。
企業型DCのメリットは数多くありますが、主な特徴には以下のような点があります。
- ・役員も加入できる
- ・掛金が多く資産運用しやすい
- ・幅広い企業が利用できる
- ・将来の期待リターンが大きく福利厚生として使いやすい
ここでは、上記の4つのメリットを解説します。
役員も加入できる
企業型DCは中退共と異なり、役員でも加入できるメリットがあります。役職に関係なく社長、役員であっても原則70歳未満の厚生年金被保険者であれば加入可能です。
掛金が多く資産運用しやすい
企業型DCは中退共と比較し、毎月拠出できる掛金が大きい点もメリットです。中退共が上限30,000円のところ、企業型DCは最高55,000円まで拠出できます。
拠出できる金額が多いほど同じ運用利率でも増える金額が大きく、より効率的に資産形成が可能です。
幅広い企業が利用できる
企業型DCと対象事業所の規模、業種に関わりなく導入が可能です。中退共を導入できない企業でも導入できるため、中退共に加入できず諦めていた企業でも従業員満足度の向上を狙えます。
将来の期待リターンが大きく福利厚生として使いやすい
企業型DCは従業員がリスク性商品(投資信託)を運用した場合、年率3~4%以上の利回りで資産形成を進められる可能性もあります。運用成績によって将来の年金額が変動するものの、運用がうまくいけば拠出額の数倍の運用益の享受が可能です。
また、仮に企業型DCを運用した結果が元本割れだった場合でも、企業は元本割れした金額を補填する必要はありません。従業員が運用商品を選ぶため、運用リスクは従業員自身が負います。
中退共のデメリットを回避するなら「企業型DC」がおすすめ
企業の福利厚生になる制度として中退共の企業側・従業員側のメリット・デメリットをそれぞれ紹介しました。
中退共が自社に合った制度かどうかを知るためには、企業と従業員の両方の視点でメリットとデメリットを理解することが大切です。
中退共は運用利回りが低く掛金も比較的低いため、従業員満足度の向上につながるかは不透明なデメリットもあります。
従業員満足度の向上や役員まで含めた社員全体の資産形成を重視する経営者の方には、企業型DCがおすすめです。企業型DCは、役員・従業員の皆さまの資産形成にもつながり、退職金制度として有効な制度です。
退職金制度の選択肢に迷ったときは、企業型DCの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
企業型確定拠出年金を導入するなら、当社「株式会社マウンティン」にご相談ください。
今なら、無料シミュレーションを提供中!導入コストや節税効果を具体的にご提示します。また、管理負担を最小限に抑えたプランで、中小企業でも安心してスタート可能です。
【当社の強み】
- ・専門家サポート:CFP・税理士が導入から運用まで徹底支援
- ・安心のシミュレーション:節税効果と資産形成を具体的に計算
- ・豊富な実績:900社超*の導入支援で培ったノウハウ
*2025年8月時点
まずは、こちらのボタンからお気軽に資料請求・お問い合わせください。